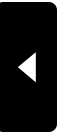新しい飼い主さんを探す会運営&預かりボランティア大募集中
毎月第2土曜日はちびねこで『新しい飼い主さんを探す会&困っていませんか?相談会』を開催中!!
毎月最終日曜日毎月最終日曜日は「C-cafe」で開催します。
 ゼロの会は「やさしい心、思いやりの心」を社会に伝えて、子供から大人まで「命を大切にする心」を共に育むことを目指しています
ゼロの会は「やさしい心、思いやりの心」を社会に伝えて、子供から大人まで「命を大切にする心」を共に育むことを目指しています
 クリックしてみてね
浜松市動物愛護教育センター
クリックしてみてね
浜松市動物愛護教育センター  HPが開きます
HPが開きます クリックしてね
クリックしてね

 ゼロの会は「やさしい心、思いやりの心」を社会に伝えて、子供から大人まで「命を大切にする心」を共に育むことを目指しています
ゼロの会は「やさしい心、思いやりの心」を社会に伝えて、子供から大人まで「命を大切にする心」を共に育むことを目指しています
 クリックしてみてね
浜松市動物愛護教育センター
クリックしてみてね
浜松市動物愛護教育センター  HPが開きます
HPが開きます クリックしてね
クリックしてね
2008年01月26日
協働の事例で紹介されました
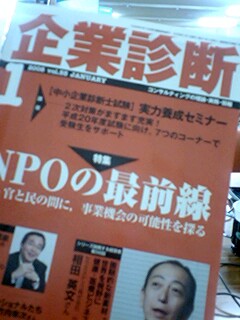 専門情報雑誌です。
専門情報雑誌です。企業診断2008年1月発行
中小企業診断士 中野眞氏による躍動するNPO 各地からのレポートから
《行政・企業と協働して 地域の問題を解決する》
事例2 地域の企業との協働『捨て犬!捨て猫!ゼロの会』
「捨て犬!捨て猫!ゼロの会」は、捨て犬や捨て猫を減らす(犬や猫を捨てる人をなくす)ことで、地域に暮らす人々の不安や困りごとを解決していこうというNPO(任意団体)である。
2007年に立ち上がったばかりの団体であるが、事業費の資金調達を地域の企業と協働で行っている。
NPOは、通常の企業と違い、売上や利益が目標ではなく、その団体の使命、理念、目的達成のために事業を行なうことが目標となる。見方を変えると、お金を使うことが重要で、そのための資金をどう集めるかがNPOの経営の課題となる。
ここでは、「捨て犬!捨て猫!ゼロの会」の事業のうち、捨て猫を減らす活動を紹介したい。これは多くの捨て猫が保険所で処分されている現状を解決するために、捨て猫の不妊手術を地域の人々に勧め、促進のために手術費用の補助をしようという活動である。そのための資金に充てる「猫基金」を設置している。
地域の店舗に呼びかけて、この「猫基金」の基金箱(写真1)の設置とPRの協力を得ている。現在、100店舗を越える店が協力をしてくれている。
考え方に賛同してくれる店舗では、レジスター横、カウンターなどに、NPOが準備した基金箱やポスター(写真2)を設置してもらい、店舗側には手間がかからない仕組みで活動を展開している。
一方、NPO側では、ブログを活用し、協力してくれる店PRし、協力店舗のイメージアップや誘客を促進している。
また、ギャラリーやコミュニティー機能を持つ店では、NPOのメンバーが撮影した写真展を開催し、活動のPRも行なっている。
さらに、このNPOでは、基金のために、また協力店舗のためにもメリットが感じられるようにと、「寄付つきの商品」企画を提案している。地元の老舗蕎麦店では、ご飯に地元産品のしらすなどを乗せた「にゃんめし」というメニューをつくった(写真3)。これは、250円で、うち50円が「猫基金」への寄付となる。
この事例から、NPOが企業と協働する場合の、ポイントが5つ浮かび上がってくる。すなわち、
①NPOは地域の課題解決をテーマにしている以上、協働の相手も地域企業がよい。
②企業側に大きな負担をかける仕組みは、企業にとって参加しにくい。
③NPO は、企業側のメリットを考えて提案する必要がある。
④NPOの課題である資金調達の方法の1つとして、広く浅く集めることが現実的である。
⑤NPOも企画力、提案力が重要である。
の5点である。
以上、協働というテーマで2つの事例を紹介してきた。NPOの活動の現場では、自らの使命、目的の達成のために、行政や企業、さらに自治会や他のNPOなどと協働することは必然的なこととなっている。
しかしながら、行政の職員や企業の担当者の不理解、NPO側の提案力不足などによってうまくいかないことが多いのも現実である。
さまざまな地域にある課題解決のために、異なる立場の組織や人々が力を合わせることは重要なことである。そのために、
①相互理解のためのコミュニケーション
②目指す姿やププロセスの共有
③事業推進のためのコーディネートを担う人材
が大切だと考える。
写真1 写真2 写真3



2007年に立ち上がったばかりの団体であるが、事業費の資金調達を地域の企業と協働で行っている。
NPOは、通常の企業と違い、売上や利益が目標ではなく、その団体の使命、理念、目的達成のために事業を行なうことが目標となる。見方を変えると、お金を使うことが重要で、そのための資金をどう集めるかがNPOの経営の課題となる。
ここでは、「捨て犬!捨て猫!ゼロの会」の事業のうち、捨て猫を減らす活動を紹介したい。これは多くの捨て猫が保険所で処分されている現状を解決するために、捨て猫の不妊手術を地域の人々に勧め、促進のために手術費用の補助をしようという活動である。そのための資金に充てる「猫基金」を設置している。
地域の店舗に呼びかけて、この「猫基金」の基金箱(写真1)の設置とPRの協力を得ている。現在、100店舗を越える店が協力をしてくれている。
考え方に賛同してくれる店舗では、レジスター横、カウンターなどに、NPOが準備した基金箱やポスター(写真2)を設置してもらい、店舗側には手間がかからない仕組みで活動を展開している。
一方、NPO側では、ブログを活用し、協力してくれる店PRし、協力店舗のイメージアップや誘客を促進している。
また、ギャラリーやコミュニティー機能を持つ店では、NPOのメンバーが撮影した写真展を開催し、活動のPRも行なっている。
さらに、このNPOでは、基金のために、また協力店舗のためにもメリットが感じられるようにと、「寄付つきの商品」企画を提案している。地元の老舗蕎麦店では、ご飯に地元産品のしらすなどを乗せた「にゃんめし」というメニューをつくった(写真3)。これは、250円で、うち50円が「猫基金」への寄付となる。
この事例から、NPOが企業と協働する場合の、ポイントが5つ浮かび上がってくる。すなわち、
①NPOは地域の課題解決をテーマにしている以上、協働の相手も地域企業がよい。
②企業側に大きな負担をかける仕組みは、企業にとって参加しにくい。
③NPO は、企業側のメリットを考えて提案する必要がある。
④NPOの課題である資金調達の方法の1つとして、広く浅く集めることが現実的である。
⑤NPOも企画力、提案力が重要である。
の5点である。
以上、協働というテーマで2つの事例を紹介してきた。NPOの活動の現場では、自らの使命、目的の達成のために、行政や企業、さらに自治会や他のNPOなどと協働することは必然的なこととなっている。
しかしながら、行政の職員や企業の担当者の不理解、NPO側の提案力不足などによってうまくいかないことが多いのも現実である。
さまざまな地域にある課題解決のために、異なる立場の組織や人々が力を合わせることは重要なことである。そのために、
①相互理解のためのコミュニケーション
②目指す姿やププロセスの共有
③事業推進のためのコーディネートを担う人材
が大切だと考える。
写真1 写真2 写真3



Posted by zero at 00:20│Comments(0)
│気になる記事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。